『スクールAI認定アドバイザー』認定制度
スクールAI認定アドバイザー制度は、アドバイザーの皆様に、『スクールAI』サービスを教育機関や自治体・教育委員会に対して広くご紹介いただき、導入後の活用促進に至るまで、ともに事業を推進していただくための制度です。
教育現場に特化した生成AI活用プラットフォームであるスクールAIの普及促進に賛同頂き、要件を満たす方を
「スクールAI認定アドバイザー」として登録致します。

スクールAI認定アドバイザーご紹介

※公開にご同意いただいたアドバイザーを掲載しております。
※所属・団体・個人別、順不同、敬称略

東北学院大学
教授
稲垣 忠
学長特別補佐
コメント・メッセージ
スクールAIを使ってプロジェクト型学習(PBL)をデザインする「情報活用型PBLシミュレーター」「ルーブリック道場」「ファシリテーショントレーナー」などを開発しています。先生方の授業づくりの助っ人として活用いただいています。生成AIができることはどんどん進化していますが、授業・学びはどう変わっていくのか。先生方、子どもたちにどんなリテラシーが求められるのか。一緒に考えていきましょう。
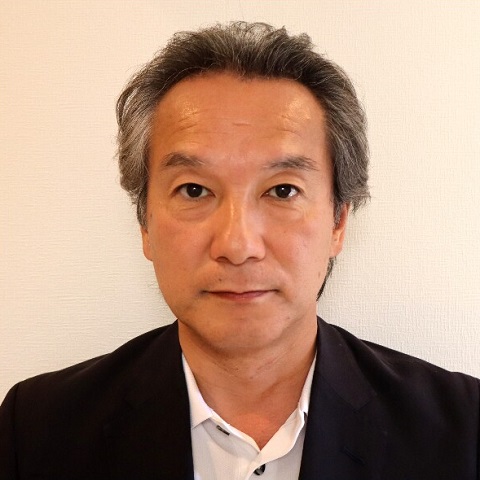
東京学芸大学
准教授
鈴木 直樹
コメント・メッセージ
AIは、個別最適な学びと協働的な学びの両立を支える重要な技術です。スクールAIの導入は、教師の役割を代替するのではなく、教師の専門性を補完し、児童・生徒の学びをより深く豊かにする可能性を秘めています。私たちは、教育現場におけるAI活用が“便利”の先にある“意味ある学び”へとつながるよう、教育的視点からの設計と実践研究を重ねていくことが求められます。スクールAIが誰一人取り残さない包摂的な教育の実現に寄与することを期待しています。

札幌国際大学
准教授
安井 政樹
文部科学省 学校DX戦略アドバイザー
コメント・メッセージ
子どもたちが、日々の学校での学びの中で生成AIの利活用を学ぶことができるスクールAI。先生たちの分身として、学びを支えたり、悩み相談にのったり、部活のアドバイスをしたりと、カスタマイズできる良さがあります。教科学習はもちろん、探究学習のサポーターとしても子どもたちの学びを伴走します。 校務利用もでき、指導案作成補助やルーブリック作成、確認問題作成などの授業支援はもちろん、所見文の下書きから添削や修正までもカバーします。 個人情報保護や年齢制限などのご心配もスクールAIは解消してくれます。 生成AI活用の第一歩をスクールAIで初めてみませんか。出前授業や教員研修で、全国の学校をサポートいたします。

中部大学
准教授
樋口 万太郎
京丹後市教育アドバイザー/オンラインサロン「先生ハウス」オーナー/ロイロ認定teacher
コメント・メッセージ
スクールAIに教育の新たな可能性を強く感じています。算数科を中心に、チャット型生成AIを活用したプロンプト設定や情報の差し込み機能により、主体的・対話的で深い学びを実現する授業づくりをサポートします。また、学習記録の可視化やフィードバック機能を通じて、学習者が自律した学習者へと成長できる環境を提供し、教員と児童生徒の双方が効果的に学び合える未来を築きます。

ヒロック初等中等部
初代学院長
蓑手 章吾
文部科学省 学校DX戦略アドバイザー/デジタル庁 デジタル推進委員/経済産業省「未来の教室」メンター
コメント・メッセージ
インターネットの登場で、知は公のものになりました。そして、生成AIの登場により、学びや成長、創造も公のものとなってきています。そんな中、学校や教育がもたらす価値や意義はなんでしょう。そんなことを考えながら、日々現場で子どもたちと新たな世界を探究しています。是非ご一緒に、新しい地図を描きましょう!
<経歴:公立小学校14年/特別支援学校4年/大学院学術修士>

神戸情報大学院大学
学長
炭谷 俊樹
ラーンネットグローバルスクール代表
コメント・メッセージ
AIは人間の仕事を奪うという懸念もありますが、一方で人の創造性や可能性を引き出す強力なツールとして活用することができます。教育現場で生成AIの導入が進む中、リスクを回避しつつ、子どもたちの創造力を高めることが重要です。スクールAIは、教員と子どもたちが安全な環境で互いに刺激し合い、成長できるプラットフォームです。私は、探究型学習の知見や技術的な視点から、このプラットフォームが多くの教育現場で有効に活用され、教育の質を向上させることを願っており、何らかのお手伝いができればと思います。皆様と共に新しい学びの可能性を開いていけることを楽しみにしています。

東京学芸大学
教授
阿部 始子
人文社会科学系 外国語・外国文化研究講座 英語科教育学分野
コメント・メッセージ
これまでの英語教育では、教室空間で英語でやりとりをしたり、英語で書いたメッセージにすぐに返事をもらったりする機会は非常に限られていました。しかし、スクールAIを活用すれば、自分に一番合ったレベルやペースで、何度も繰り返し「自分の英語が通じた!」という成功体験を積み重ねることができます。また、その会話履歴や記入履歴を学習者が振り返ることで自律学習を促すツールとしても活用することができ、教師もそれぞれの学習者に適切なサポート体制を整えることができます。AIとの成功体験を通して自信を育み、実際に人を相手にしたコミュニケーションへとつないでいく新しい時代の英語学習ツールとして、スクールAIは大きな意味を持っていると思います。

青山学院大学
客員研究員
梅野 哲
相模原市立中野中学校 ️総括教諭
スクールAI認定プロンプトイノベーター
コメント・メッセージ
学校での生成AI活用には、教師自身が「何のために使うのか」という目的を明確にし、「どのように使うのか」を子どもたちに適切に支援することが求められます。そうした中で、生成AIをうまく活用できている子どもたちは、AIを「協働相手」として捉え、思考を広げたり深めたりしながら、自ら必要な知識を主体的に獲得しています。このような「AIリテラシー」を育むには、教師による授業デザインの工夫が不可欠です。私は、教師の授業研究を支援し、対話を通して学びをデザインする「授業シミュレーターアプリ」を『スクールAI』のプラットフォームで開発しました。『スクールAI』の魅力は、目的に合ったプロンプトを事前に設定できる点にあります。教師・生徒の支援となるこのプラットフォームで、生成AIの教育活用をともに探究しましょう!

玉川大学
教授
濵田 英毅
教育学部 日本近現代史(歴史資料論)
コメント・メッセージ
生成AIは、あなたにとって自転車や車のようなものです。一台あれば、どこにでも行くことが出来ます。ただし、その便利さを本当に享受するためには、子供の頃から交通ルール(リテラシー)を学び、上手に操縦するための方法を「実践と共に理解する」必要がありますよね。あなたは生成AIを「実践と共に理解する」ことが出来ていますか?
もし、上手な操縦方法を学びたいとお考えでしたら、研修の講師として私にご用命ください。生成AIを理解するには、機械としての特性を把握することも重要ですが、私はあえて「生成AIを人に例えてご説明」します。生成AIとどう向き合えばよいか、そして生成AIとの対話を続けるための原理・原則が納得できれば、「応用が利くノウハウ」が身につくでしょう。
<近年は専門領域を基盤としたSTEAM教育の実践に取り組む。「臨場感」ある歴史の理解を重視し、「臨場感」を再現するためのストーリーテリングの技法開発や、3Dプリンターを活用した教材開発に注力。スクールAIを利用して、生成AIを活用した教材「歴史人物シミュレーター」を開発。>
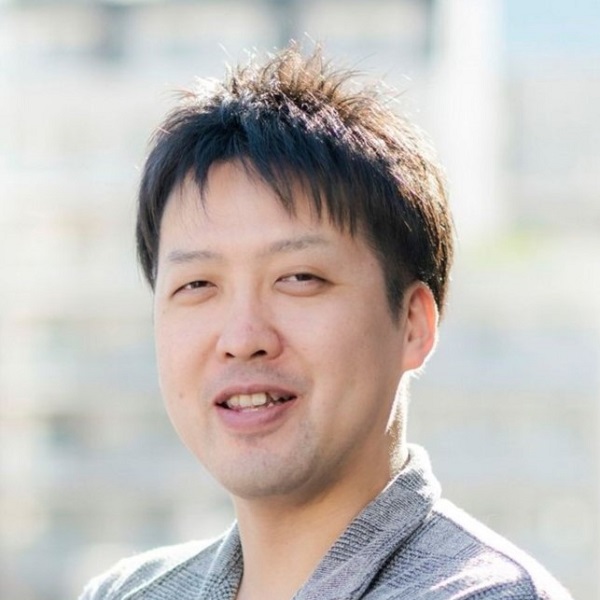
スクールエージェント株式会社
代表取締役
田中 善将
文部科学省 学校DX戦略アドバイザー/デジタル庁 デジタル推進委員/関東第一高等学校 AI駆動型探究アドバイザー
コメント・メッセージ
AIエージェントの考え方は、今は斬新ですが、いずれ教育界でも主軸になります。自動化された個別学習は、すでに驚異的な効果を生み始めています。
学び方を、子どもたちと先生方が一緒に考え文化形成するために、スクールAIは最適です。検索的利用だけではなく、情報を編集し、組み上げていく中で新たな気づきを得る、そんなチャンスを教室で増やす事につながります。
1番大切な先生方の『どう学ぶか』を仕掛ける時間も、働き方を変える中で捻出できるでしょう。
スクールAIを使いながらAIエージェント時代の学びを一緒に形作っていきましょう!
<トキワ松学園高等学校 情報科講師/Google for Education 認定イノベーター/Professional ChromeOS Administrator>

岡山大学
准教授
江尻 寛正
教職員支援機構(NITS)フェロー(2024~)
コメント・メッセージ
元・教育委員会指導主事。教師の学びについて研究中。AI時代においてこそ、人が人に関わり、問いを共有し、創造性を育むことがますます重要になると考えています。スクールAIでは、自身に合わせたカスタマイズができます。その良さを活かし、AIとどのような関係性を構築していくのかについて、インストラクショナル・デザインの知見を活かしながら、これからの授業や学びをともに考えていけたらと思います。
<経歴:「指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料」小学校外国語・外国語活動 作成委員(2020、国立教育政策研究所)/修士(教授システム学)>

合同会社未来教育デザイン
代表
平井 聡一郎
文部科学省学校DX戦略アドバイザー/ 総務省 地域情報化アドバイザー/デジタル庁 デジタル推進委員
コメント・メッセージ
生成AIは学校DX推進の鍵を握っているツールだと考えています。前例踏襲のガチガチに固まった学校組織をunlearnさせるツールとも言えます。ただ、ちょっと新しいツールゆえに、これまでの学校文化にはすぐには馴染みません。スクールAIにはそんな生成AIを学校に馴染ませる役割を期待しています。
スクールAIに関わる皆さんととも日本の学校DXを一気に加速させて、学校をもっとワクワクする場所にしていきましょう。
<青森県教育改革有識者会議常任委員、 福井県学校DX推進アドバイザー、 厚沢部町義務教育学校整備検討会議委員他>


