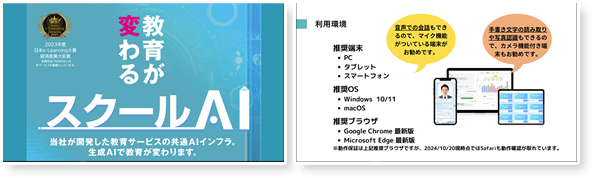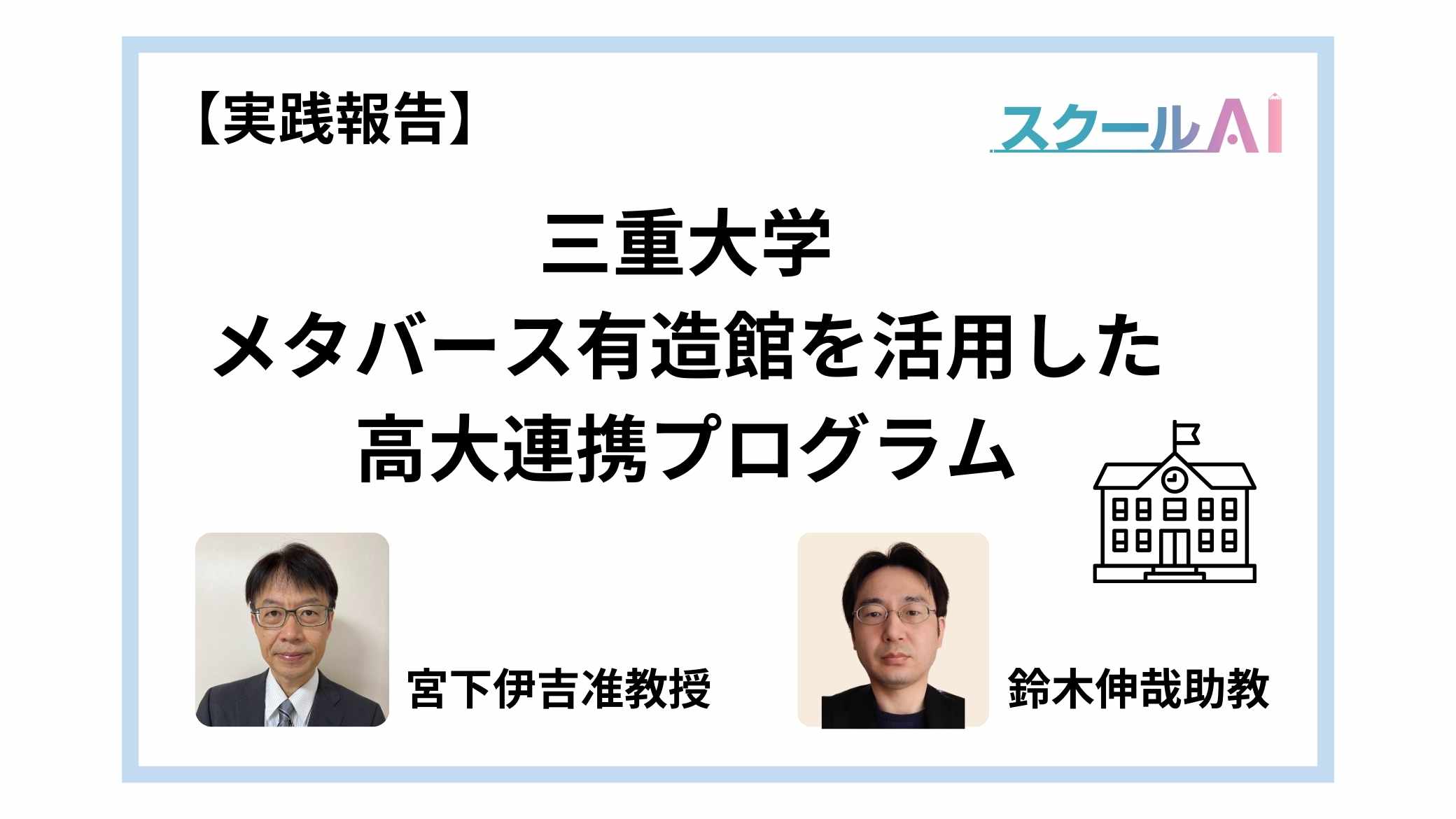
【実践報告】メタバース有造館を活用した高大連携プログラム
※2024年7月実施
国立大学法人 三重大学
宮下伊吉准教授
鈴木伸哉助教
モード名:メタバース有造館を活用した高大連携プログラム
対象:高校2年生(文理探究コース)
教科:地域課題探究(探究学習)
▼ポイント
・メタバース空間「有造館」を活用し、高校生の地域課題探究活動を支援
・「スクールAI」による生成AIの活用で、質問対応とアドバイスを効率化
・高校生が大学生メンターとの対話を通じて自主的に課題に取り組む体験を提供
プログラムの概要
三重県内の公立高校文理探究コースで学ぶ高校2年生35名が8グループに分かれ、ビジネスプランを考えるという探究活動において、三重大学のメタバース有造館に接続して三重大生に質問し、文理探究メンターである三重大生が「スクールAI」を活用してメタバース内で回答するやりとりを各グループ2回実践しました。
※オンライン(メタバース有造館)で、かつ限られた時間での、高校生からの疑問や相談に対しての回答を大学生が考える手段として「スクールAI」を活用。高校生にも分かりやすい内容になるようあらかじめプロンプトで調整して臨機応変に対応。
高校生の8グループは、7月30日に三重大学に来学し、三重県内の自治体(市役所)等の地域関係者の前でグループプレゼンを行いました。
宮下伊吉准教授からのコメント
今回のプロジェクト「メタバース有造館を活用した高大連携プログラム」の成果は、地域の課題探究に取り組む高校生をメタバース空間内で三重大生が生成AIを活用しながらサポートすることができたことです。プログラム実施にあたり、文理探究メンターとして協力いただく三重大生に対して、生成AIに関する事前講習の講師を、教育×生成AIのサービス開発プラットフォーム「スクールAI」を展開している(株)みんがく代表 佐藤雄太氏に依頼するとともに、「スクールAI」を実際に利用するにあたり、適切な助言もいただくことができました。特に、高校生の探究活動への自主的な取り組みにつながるようにするために、生成AIのプロンプト(指示・命令文)の設定をどのように調整すれば、意図した回答が出力されるかをあらかじめ試行錯誤することができたことがとても助かりました。
【教育におけるAI活用の可能性について】
社会でのAI活用が広がっていくことで今後さらに教育におけるAI活用の可能性が高まると考えています。特に高校生が生成AIを活用するにはまだ様々なハードルがあるほか、大学生も事前の理解が必要であるため、生成AIを活用するにあたり、注意すべき点も含めたメリットデメリットなどの理解や実際に試してみることができる環境が必要ではないでしょうか。
鈴木伸哉助教からのコメント
高大接続の特別プログラムとして、三重県内公立高校の探究学習支援を実施し無事プレゼンを終えることができました。地域の関係者にも発表を聞いていただき、好意的なコメントをいただくことができました。発表に至るまでの過程において、高校生からの相談や質問への対応は三重大学の学生に協力してもらいましたが、生成AIについて前もって理解を深めてもらうために、みんがく様にはセミナーで講師をしていただきました。私ども教員にも打合せを通じて生成AIやスクールAIの利用についてのアドバイスを多くいただき、大変参考になりました。
【教育におけるAI活用の可能性について】
まだ万能ではなく、得意不得意があり、それを見極める能力や適切な利用法の習得が求められるのが現状ではないでしょうか。リテラシーとして身に着けさせるなど、今後はAI活用教育のような新しい分野も広がっていく可能性がありますので、注目していきたいと考えております。
まとめ
スクールAIに関する資料をご提供しております。資料のダウンロードは以下よりお願いします。